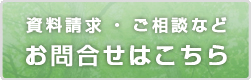ホーム > タグ > 豆知識
豆知識
中国産と国産、それぞれの特徴と工場の現状
- 2012-10-25 (木)
- 転職コンサルタント~虎の巻~
アパレル商品でよく見る生産地といえば、中国です。
アパレルだけでなく、雑貨などにもよく「MADE IN CHINA」の表記を見かけます。
中国に発注する場合のメリットは、とにかく安く依頼できるということ。制作費が安ければ、それだけ消費者にも安く提供することができます。
また、大量発注を依頼するにも、中国は向いています。
中国には広い工場があり、その中で多くの人々が働き、次々と新しい商品を生み出しています。輸送にかかる時間などの関係で、短納期のものは中国には依頼することは少ないと思います。そうすると、長期間販売する同一商品を依頼することとなり、大量の商品を生み出すことができます。
デメリットとしては、国民性からか、仕事が雑、ということがあげられるでしょう。中国との取引をしている人は、最初のうちは安定しない品質に嘆くことが多いようです。
しかし、同一商品を長期間生産することが多いので、徐々に品質は安定してきます。
中国の工場で大量生産を行い、成功した例としてよくユニクロが挙げられていますが、ユニクロは中国の工場に日本の責任者が常駐していました。その責任者が品質管理を徹底していることで、安定した品質の商品を生み出すことが可能になったのです。
一方、日本で生産される商品は短期で納品することが可能です。
ギリギリまで流行を見極めることもできますし、大量生産をする必要がないことから、大量に売れ残ってしまう事態も避けられます。
中国にある工場は、一つのブランドの専属工場であることがほとんどですが、日本の工場は、一つの工場で複数のブランドの商品を生産していることはめずらしいことではありません。
そのため、あまりにも短い納期だと工場がキャパオーバーになってしまう可能性もあり、下請工場にまわされ、粗悪な商品になってしまうことも考えられます。
日本の工場は、中国の工場に比べると安定していそうで安定していません。これが、今後の大きな課題になってくるでしょう。
OEM生産と、ODM生産の違いとは?
- 2011-12-08 (木)
- 転職コンサルタント~虎の巻~
アパレル業界を志す人ならば知っておきたい言葉としてSPAがありますが、それと一緒に覚えておきたい言葉が「OEM」と「ODM」です。似たような言葉ですが、OEMとODMの違いは何でしょうか?
・OEMとは
OEMとは、Original Equipment Manufacturing、または Original Equipment Manufacturerの略語で、委託者のブランドで製品を生産すること、または生産するメーカのことです。日本では「相手先ブランド名製造」や「納入先商標による受託製造」などと訳されます。
OEM生産は、発注する小売り側が商品企画を行い、製造を相手先に託し、サンプルのチェックなどを自己責任で行います。自社生産から撤退してOEM生産に切り替えることでコストを削減したり、自社生産が追いつかない時に他社に委託するなど、有効に利用されることが多いようです。
また、中小企業などの企業においては、相手先の営業力を活用できるといったメリットもあります。
・ODMとは
基本的にはOEM生産と変わりませんが、ODMでは商品企画までも仕入れ先の業者に任せます。そして製品のサンプルを確認し、購入するか否かを決める方法です。
メリットとしては、製品サンプルになるまでのプロセスを発注側が省くことができることでしょう。また、デザイナーやパタンナーなどの企画開発担当などを社内に置かなくてもいいため、人件費削減になります。
この生産方法を採用しているのがForever21で、バリエーションが豊富であることが売れるポイントとなっています。
この成功から、SPAを採用している多くのアパレル業者がODMに注目しているようですが、SPAからODMに切り替えることによってどのようなメリットやデメリットが生じることになるのかをしっかりと理解しておくべきでしょう。
売る能力が長けているSPA企業では切り変えてもメリットになるでしょうが、商品の完成度やデザインにこだわるSPA企業がODM生産に切り替えたところで問題が生じてしまうことになるでしょう。
大手ではSPA生産が多いのですが、OEM生産とODM生産についてもその違いと特徴を知り、就職・転職に役立ててみてください。
服だけにとどまらない! 「ファッションビジネス」の動向とは?
- 2011-11-04 (金)
- CASSからのお知らせ
近年のファッションビジネスの特徴は、「アパレルメーカーを中心に幅広い産業が寄り集まった裾野が広いビジネス」であるということです。すなわち、消費者が求める「個性」をトータルにコーディネートするビジネスモデルであり、衣料品を中心に、そこから派生して、美と健康、雑貨、インテリア、食品、音楽に至るまで広く提供することを目指しています。消費者は同じブランドのコンセプトで服や雑貨を揃え、時にはカフェでお茶することができます。
その一例として、国内大手のアパレルメーカーである(株)ファイブフォックスの展開する『コムサ・デ・モード』が、1996年に異業種参入で始めた「カフェ・コムサ」が挙げられます。あるブランドのコンセプトが日々の生活のあらゆるシーンに浸透するよう様々な企画を行うファッションブランドですが、ファッションはリサーチを重ねても、何がトレンドになるのか予測をつけにくい分野だと言われており、現代の多様な価値観の中で常に好まれるスタイルを提案し続けるには、
周到な市場調査と計算されたブランディングが欠かせません。大手のような力のある企業は、一つのコンセプトにこだわらず、価格帯や対象年齢によりコンセプトの異なるいくつものブランドを抱え、直営店に限らずショッピングセンター、スーパー、百貨店と、ターゲット層に合わせたチャネル展開を強みとしています。ひとつひとつのコンセプトに、付帯ビジネスを巻き込むことで巨大なファッション市場を形成していくのです。
このようなファッショントレンドの中核となるのはアパレルメーカーであり、大半は「総合アパレル」と呼ばれ、年齢も対象も幅広くカバーした総合的な衣料を中心に様々なアイテムを消費者へ提供します。そのほかにも各分野に特化した「専門アパレル」があり、レディース、メンズ、子ども服、和装などの分野によって扱うブランドが分かれています。特に子ども服は歴史が長く、老舗企業が多いことで知られています。たいていのアパレルメーカーでは縫製は外注していますが、その多くが人件費の安い海外で行われています。
一方、高い技術力を誇る国内縫製にこだわるブランドもあり、縫製の質の高さを強みとし海外縫製の商品との差別化を図っているようです。コストを抑えて大量生産をするか、限定生産でも高級衣料としての高い価格で採算をとるか、ファッションビジネスの世界では二極化が進んでいます。
昨今では、既製服をデザイン・販売している企業はアパレルメーカーにとどまらず、百貨店やスーパー、専門店などの流通業、原材料の生産・製造工場、繊維業、商社、さらに食品や化粧品、メディアなども市場に参入してきています。かつては業種の住み分けがはっきりしており、たとえば繊維業や生産・製造工場は、紡績や染色、素材の提供など「製造」の部分にしか関わっていませんでしたが、現在では独自のブランドを立ち上げて消費者の手に渡るまでの流通を手がける企業もあり、関わる業種の間に垣根がなくなってきています。
「ファッション」という概念は、もはや服装だけではなく、衣食住という生活をトータルコーディネートする指針となっているのです。
ホーム > タグ > 豆知識